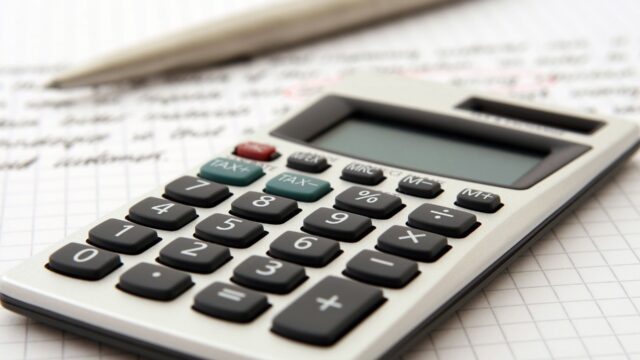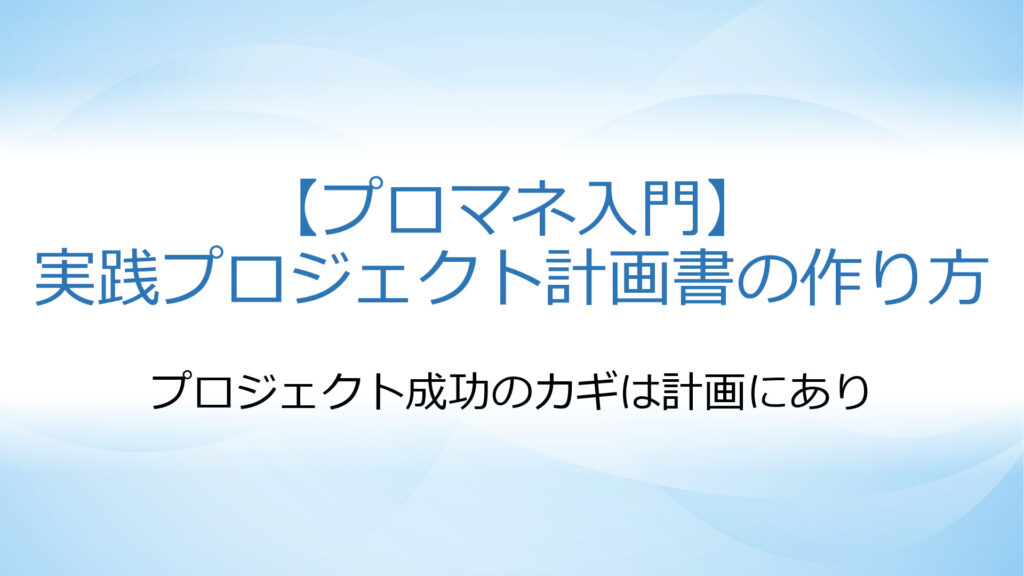EVMによるマネジメント手法 – EVMの必要性と作成・運用の要点

【目次】
・EVMの説明
- EVMとは
- EVMの目的
・EVM作成と運用
- EVMの作成方法
- EVMの運用ポイント
・活用ポイント
- よくある誤解と落とし穴
- 導入ロードマップ
・まとめ
EVMの説明
EVMは計画・進捗・コストを一つの物差しで可視化し、早期警戒と納得の意思決定を支える手法です。
このEVMの目的と指標について解説します。
EVMと連動した進捗管理表のサンプルはこちらからダウンロードできます。
EVMとは
EVM(出来高管理)は、プロジェクトの計画上の進み具合・実際の進み具合・使ったコストを同じ物差し(お金=価値)で測り、現在の健全性と完了時の見込みを早期に把握する管理手法です。
核になる3つの値を押さえましょう。
- PV(Planned Value:計画出来高)
いま時点までに計画上進んでいるはずの価値の累計。 - EV(Earned Value:実績出来高)
いま時点までに実際に完了した価値の累計。 - AC(Actual Cost:実コスト)
いま時点までに実際に支出したコストの累計。
この3つを組み合わせると、
- 進捗の遅れ/先行(スケジュールの健全性)
- コストの超過/節約(費用の健全性)
を数字で同時に把握できます。
グラフや感覚に頼らず、意思決定につながる数値で会話できるのがEVMの価値です。
EVMの目的
(1) 早期警戒(アーリー・ワーニング)
EVMは小さなブレを数値で拾います。
EVがPVを下回れば「遅れ」が、EVがACを下回れば「コスト超過」が分かります。
現場体感より早く兆候を捉え、小さいうちに是正できます。
(2) 合意形成と説明責任
「忙しい」「大変」ではなく、CPIやSPIといった客観指標で語れるため、経営層・顧客・他部門への説明が短時間で納得感を得やすくなります。
対策の優先順位付けも明確です。
(3) 組織的学習(見積と運用の改善)
EVMは見積りの精度や運用のクセを反映します。
完了時予測(EAC)の差分を振り返るほど、次回の見積・計画の質が上がります。
単発の“監視”ではなく、継続的改善の仕組みです。
EVMの主要指標
まずは以下を覚えてください(“1.00が中立”の感覚が大事)。
- CPI(Cost Performance Index)= EV / AC
1.00以上:コスト効率良好、未満:超過傾向 - SPI(Schedule Performance Index)= EV / PV
1.00以上:進捗前倒し、未満:遅れ傾向 - BAC(Budget At Completion):当初総予算
- EAC(Estimate At Completion):完了時の予測コスト
- ETC(Estimate To Complete)= EAC − AC:残りに必要なコスト
- VAC(Variance At Completion)= BAC − EAC:完了時の差額(+は余剰、−は不足)
- TCPI(To-Complete Performance Index)
- TCPI(BAC)=(BAC − EV) / (BAC − AC)(当初予算死守に必要な残り効率)
- TCPI(EAC)=(BAC − EV) / (EAC − AC)(更新後予算死守に必要な残り効率)
1.00超は「これから今より良い効率が必要」のサイン。
EVM作成と運用
EVMの作成方法
「どのツールでも共通」の作り方を、考え方→具体ステップの順で整理します。
考え方の土台
- 価値の単位を決める
基本はコスト(円/時間×単価)で統一します。
価値を金額化することでPV・EV・ACを比較しやすくなります。
スケジュールと直接連動させる場合、金額ではなく工数で比較する方法もあります。 - WBS(作業分解)を用意
タスクの抜け・重複を抑え、責任者・開始・終了・見積工数・単価をひとつずつ紐づけられる粒度にします。 - ベースライン(計画)を固める
“いま時点までのPV”を算出できるよう、タスクに計画進捗曲線(単純均等でも良い)を持たせます。 - 完了の定義(DoD)を明文化
0%/50%/100%の基準をレビュー合格・受入完了などで具体化し、EVの主観ブレを防ぎます。 - 実績収集の仕組み
タスクごとに完了率(%)と実コストが定期的に更新される運用を決めます
(例:日次は担当、週次はPM集約)。
作成手順
- Step 1:WBSの確定とBAC算定
各タスクに見積工数×単価を掛けてコスト化、合計がBAC。 - Step 2:計画進捗(PV曲線)の設計
期間均等配分が最小構成。 - Step 3:実績の記録(EV/ACの更新)
タスクの完了率×見積コスト=EV(タスク)を累計。
支払い・工数計上・外注費などACを累計。 - Step 4:集計と指標計算
全タスクのPV/EV/ACを日付時点で合計し、CPI・SPIを算出。
ポイントは、PV・EV・ACを“同じ価値尺度”で横並びにすること。
これさえ守れば、シンプルな作りでもEVMは十分機能します。
EVMの運用ポイント
5.1 閾値(しきい値)で素早く仕分け
- CPI < 0.95:コスト超過傾向(赤)
- SPI < 0.95:進捗遅れ傾向(赤)
- 0.95〜1.05:警戒域(黄)/ >1.05:良好(緑)
※数字は“即アクション目安”。プロジェクト特性で調整してOK。
5.2 週次30分レビュー
- ダッシュボード俯瞰(10分)
PV/EV/AC、CPI/SPI、VACの方向性を確認。 - 赤・黄の原因→対策(15分)
1タスク3分で原因の事実を押さえ、対策・期限・責任者を決める。 - 共有・記録(5分)
議事の要点(指標→原因→対策→期限)を配信。
5.3 役割分担
- 担当者:期日までに完了率と実績工数/コストを記録。
- PM:しきい値で仕分け、リスク/課題の是正と予測の説明責任を担う。
- ステークホルダー:指標に基づく意思決定(増員・リスケ・スコープ最適化等)を支援。
5.4 EVの“客観性”を守る
- 完了の定義をプロセスごとに具体化(例:設計=レビュー合格、テスト=合格率×欠陥密度基準)。
- 「80%進んでます」は禁止。達成条件に紐づけて%を決める。
5.5 TCPIで「残りの頑張り具合」を可視化
TCPI > 1.05なら、「この先は今まで以上の効率が必要」と伝えられます。
増員・手戻り抑制・外注最適化など、打ち手の強度を合意しやすくなります。
活用ポイント
よくある誤解と落とし穴
EVMは“統制手法”であって“叱責装置”ではない
→ 目的は“早期是正”。数字で責めず、数字で支える。
EVを人の主観で決める
→ DoDを明文化。レビュー/受入に結び付けて%を確定。
PVの形が現実とズレる
→ 均等配分で始め、偏るタスクは配点見直し。月次で微修正OK。
進捗グラフだけで満足
→ グラフは結果。CPI・SPIの値→原因→対策→期限で回す。
“過剰な精緻化”で運用が負担になる
→ 列・指標は最小から。赤・黄・緑の仕分けが安定したら拡張。
外注費/間接費がACに入らない
→ 支出は原則すべてACに計上。見逃すと“黒字に見える赤字”。
EACの前提が曖昧
→ 会議で「今回はEAC₁採用」と明示して合意。議事に残す。
導入ロードマップ
週1回の軽量EVMからスタート
- WBSの重要タスクだけでPV/EV/ACを作り、CPI・SPIで仕分け。
- 2〜3スプリント回して“回る型”を固める。
対象を拡大
- 成果が実感できたら全WBSに展開。EAC・TCPIまで定着させる。
組織ナレッジ化
- 毎案件でEACと実績差を振り返り、見積係数・生産性ベンチマークを更新。
- 学習が進むほど、計画精度が上がり意思決定が速くなる。
まとめ
- EVMは“価値”という共通物差しで、計画(PV)・進捗(EV)・コスト(AC)を一体管理する仕組み。
- 最低限の指標(CPI/SPI・EAC・TCPI)で、早期警戒→原因特定→対策合意が素早く回る。
- 作成の肝は、価値の統一・DoDの明文化・ベースラインの整備・実績収集の仕組み化。
- 運用はしきい値で仕分け→30分レビュー→予測更新の型で軽く回す。
- 小さく始めて学びを蓄積すれば、次のプロジェクトの見積と統制が確実に賢くなる。
EVMは“難しい管理会計”ではありません。
小さく始めて、指標で会話する——この一歩が、納期・品質・コストの全部を守る最短ルートです。