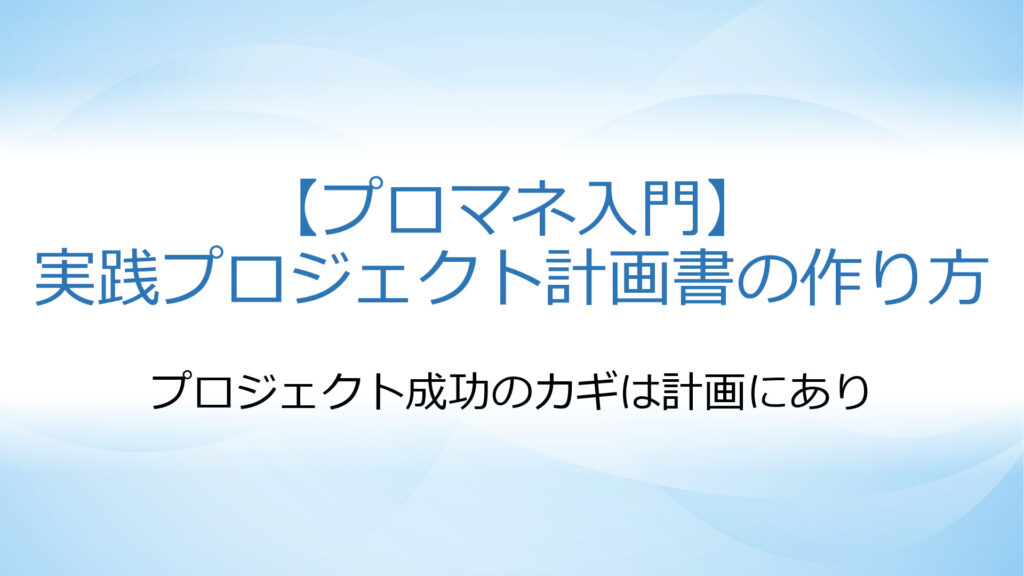【目次】
・概要
・フェーズ終結
- 実施すべき作業が完了していること
- 成果物の受入が完了していること
- 残課題と申し送り事項
- 振り返り
・プロジェクト終結
- 契約が完了していることを確認する
- 納品
- 顧客からフィードバックをもらう
・プロジェクトが中断した場合
概要
工程完了時やプロジェクト終結するときに事務的な手続きや報告など行いますが、それ以外にも取り組むべきことがいくつかあります。
それら「取り組むべきこと」を行うことで、次の工程をスムーズに進めたり、今後のプロジェクトを効率化することができる可能性があります
フェーズ終結
実施すべき作業が完了していること
これは当然のことですが、その工程で作成した成果物や顧客と取り交わした作業が完了していることを確認します。
進捗確認の中で気を付けていれば問題は起きにくいですが、スコープ・ベースラインと比較して抜け漏れがないかチェックします。
注意すべきは、顧客との会話の中で出てきた課題や依頼事項です。
会議の中で話題に上がった課題やタスクが曖昧にならないよう、しっかり課題一覧と議事録で管理するようにします。
気になるようでしたら、事前に抜け漏れがないかステークホルダーと会話するとよいでしょう。
成果物の受入が完了していること
成果物が顧客に受け入れてもらっていることを確認します。
成果物の作成状況は進捗管理で確認されているので問題ないでしょうが、それらが受け入れられているか確認する必要があります。
特に、要件定義書や外部設計書に顧客の承認印をいただけているか注意すべきです。
次フェーズに入った後に顧客から「承認していない」「上長からNGもらった」と言われる場合があります。
もし顧客が承認印を押すことを避けているときは、後から変更することを想定している可能性が高いです。
残課題と申し送り事項
フェーズ内で全ての作業が完了しているのが理想ですが、事情により次フェーズに持ち越す課題や作業が発生することがあります。
そのような時は残課題と対応方法、予定時期を明確化して顧客と合意を取ったうえで、次工程への申し送り事項とします。
そして、この残課題を次フェーズのWBSにするか課題管理で対処します。
いずれにせよ前フェーズの積み残しであるため最優先で対応する必要があります。
振り返り
チームメンバを集めて作業内容の振り返りを行います。
フェーズ終結では、実施した作業内容について「良かったこと」「悪かったこと」を振り返り、次フェーズに向けて改善点を検討します。
プロジェクト完了時には、プロジェクト全体の振り返りを行います。
この振り返りは、プロマネ含めてチームメンバが成長する最高の機会です。
日常の業務では気づかないことも後から振り返ると反省点は見つかりますし、良かったところを意識できれば次に活かせます。
また他メンバから指摘されることで新しい気づきも得られます。
他メンバの「こんなところに気を付けている」といった暗黙知(属人的な知識)を知ることができれば、それを自分に取り込むこともできます。
プロジェクト終結
プロジェクト終結では、フェーズ終結で実施することに加えて以下の対応を行います。
契約が完了していることを確認する
契約関連は取り扱いを間違えると大問題になります。
納品や検収など、契約完了手続きが完了していることを確認します。
納品
成果物の納品が完了していることを確認します。
契約時に取り決めた内容で成果物が納品されていることを確認し、内容に問題がないことを顧客に合意します。
ちなみに納品方法は顧客によって異なります。
今でも紙納品の場合もありますし、納品の細かいルールが取り決められている場合もあります。
これらは契約時点で明確にしていると思いますが、プロジェクト立ち上げ時点で顧客とすり合わせている必要があります。
「全て紙に印刷して納品する」と言われた場合、その作業だけで大量の工数が発生することもあります。
顧客からフィードバックをもらう
開発者側と顧客の視点では異なる点が多いのですが、システム開発を請負うベンダが意識すべきは利用する顧客が満足できるシステムを提供することです。
顧客には、システムを導入して実現したい目標があり、それがシステム導入することで実現していることが大切です。
そのため顧客からのフィードバックをもらうことで、チームやメンバに新しい気づきを与え、成長につなげることができます。
どのような対応をすれば顧客に満足してもらえるか知ることで、次から取るべき選択肢が増えます。
プロジェクトが中断した場合
プロジェクトの失敗、事業環境の変化に伴うプロジェクト意義の喪失など、プロジェクトは中断される場合があります。
もし契約関連で揉めるようであれば必要に応じて対処していきますが、それとは別に成果物の整理などする必要があります。
中断したとしても、それまで作成した中間成果物は納品することになります。
また外部ベンダに発注している場合は、逆に中間成果物を受領します。