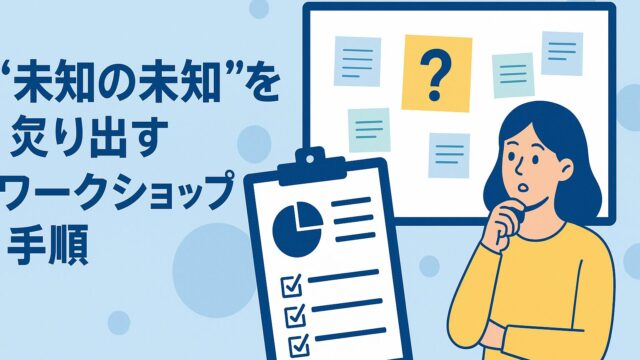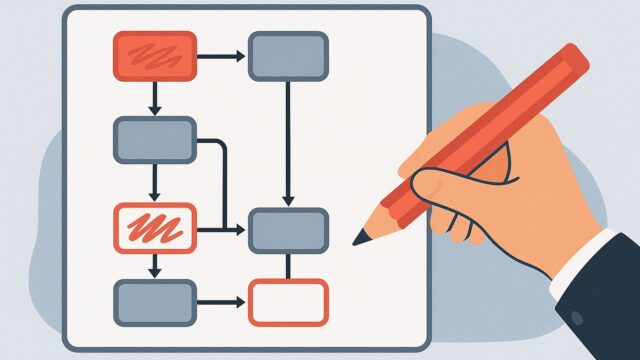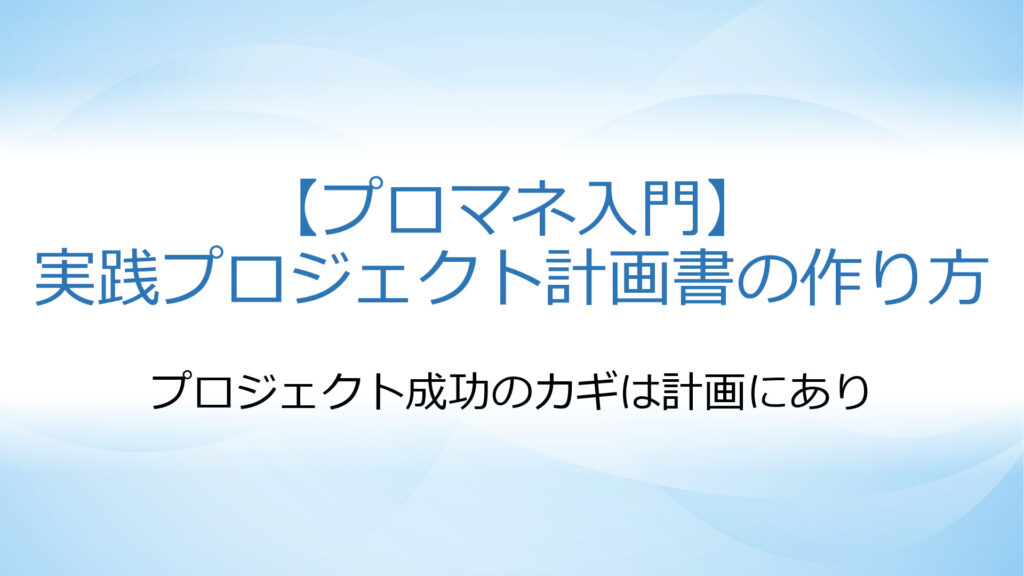実務で使えるシステム開発のための見積り根拠の書き方カタログ入門

【目次】
・なぜ「見積り根拠」がそんなに大事?
・見積り根拠とは何か
・見積り根拠を書くときの基本ルール
・手法別・見積り根拠の書き方サンプル
・見積り根拠カタログ:書くべき項目と例文集
・よくあるNGパターンと改善例
・見積り根拠をレビュー・更新するポイント
・まとめ
なぜ「見積り根拠」がそんなに大事?
システム開発の見積りレビューで、こんなやり取りをしたことはありませんか。
- 上司「この工数の根拠は?」
- PM「えっと、過去の経験から…」
- 顧客「もう少し説明してもらえますか?」
見積りの数字そのものよりも、「なぜその数字になったのか」を説明できるかどうかで、
相手の納得感や信頼度が大きく変わります。
ここで必要になるのが「見積り根拠」です。
本記事では、システム開発のプロジェクトで使いやすい 見積り根拠の書き方 を、テンプレート感覚で使える「カタログ形式」で整理します。
そのまま文章を少し変えて流用できるように、具体例も合わせて紹介します。
見積り根拠とは何か
見積り根拠の定義
見積り根拠とは、見積りの数字(工数・期間・コスト)に対して「なぜその値なのか」を説明するための情報や前提条件のことです。
例えば、以下のような情報が含まれます。
- 前提条件(やらないこと・やることの範囲)
- 使用した見積り手法(類推、ボトムアップ、FP法、ストーリーポイントなど)
- 元になった過去実績や参考資料
- 工数や期間を決める際に使った計算式
- リスクと不確実性を踏まえたバッファの考え方
見積り根拠を書く目的
見積り根拠を書く目的は主に次の3つです。
- 説明責任を果たすため
・顧客・上司・ステークホルダーに対して、「なんとなく」ではなく論理的に説明できる。 - 将来の自分とチームを守るため
・後から「なぜこの工数で合意したのか」を思い出せる。
・手戻りや追加要望が出たときに、「当初の前提と違う」ことを客観的に示せる。 - 見積りの品質を上げるため
・根拠を言語化することで、漏れや矛盾に気づきやすくなる。
・他メンバーのレビューを受けやすくなり、見積り精度が改善される。
見積り根拠を書くときの基本ルール
ここからは、どんなプロジェクトでも共通して使える「書き方の基本」を押さえておきます。
数字とセットで「根拠」を書く
NG例:
- 「実装:80時間」
- 「テスト:40時間」
OK例:
- 「実装:80時間(既存モジュール流用率70%、新規画面4画面×各8時間+共通部品16時間+レビュー時間16時間を想定)」
- 「テスト:40時間(単体テストケース約40件、1件あたり0.8時間+バグ修正レビュー含む)」
数字だけではなく計算の内訳を書くことで、後から見直したときも意味が分かります。
前提条件と範囲を明確にする
見積り根拠は、以下のような前提とセットで書くとブレが減ります。
- 対象スコープ(どこまで含めるか)
- 対象外(やらないこと)
- 役割分担(どこまで自社/相手が担当するか)
- 使う技術・ツールの想定
- 品質レベル(テスト範囲・レビュー回数など)
手法別・見積り根拠の書き方サンプル
ここでは、代表的な見積り手法ごとに、根拠の書き方例を紹介します。
類推見積り(類似プロジェクトから推定)
想定シナリオ
- 過去に似たような案件を経験している
- 大まかな規模感は掴めるが、詳細はこれから
書き方例
本案件は、2023年実施の「在庫管理システム刷新」と機能構成・技術スタックが類似しているため、当該プロジェクトの実績工数(合計1,200時間)をベースとした類推見積りとした。
データ項目数が約1.2倍であることから、実装・テスト工数に1.2倍の係数を適用し、要件定義・設計はほぼ同等とみなして算出している。
ポイントは、
- どの過去案件を参照したか
- どの部分を同じとみなしたか
- どこを何倍・何%で補正したか
を明確に書くことです。
ボトムアップ見積り(WBSベース)
想定シナリオ
- WBSを作成し、タスクごとに工数を積み上げる
書き方例
要件定義〜総合テストまでの工程をWBSに分解し、各タスクに対して担当者1名あたりの標準作業時間を設定して積み上げた。
要件定義は「現行調査」「ToBe整理」「要件定義書作成」「レビュー対応」の4タスクとし、各タスクの工数は過去3案件の平均値(例:現行調査 24時間、要件定義書作成 40時間)をベースに算出している。
ここでは、
- 「WBSで分解した」こと
- 「各タスクの時間の根拠」がどこから来ているか
を書きます。
パラメトリック見積り(規模×係数)
想定シナリオ
- 画面数、帳票数、IF本数などから工数を算出
書き方例
実装・単体テスト工数は、画面数・帳票数・IF本数を基準としたパラメトリック見積りとした。
- 業務画面:15画面 × 10時間/画面 = 150時間
- 参照系帳票:5帳票 × 8時間/帳票 = 40時間
- 外部IF:3本 × 20時間/本 = 60時間
各単価は、直近2案件の実績(平均値)と今回の難易度(中程度)を踏まえ設定している。
「何に対して」「いくらの単価をかけたのか」を、式で見せると相手も納得しやすくなります。
見積り根拠カタログ:書くべき項目と例文集
ここからがメインの「カタログ」部分です。
実際の見積り資料や見積り根拠書に、そのままコピペして調整しやすい形で整理します。
プロジェクト全体の前提条件
項目例
- 対象スコープ
- 対象外
- 役割分担
- 品質条件
- 前提となるインフラ/環境
- 前提となる情報提供
例文
- 「本見積りは、要件定義〜総合テストまでを対象とし、本番移行後の保守・運用は含まない。」
- 「インフラ環境(サーバ、ネットワーク、OS)は顧客側で構築・提供されることを前提とする。」
- 「画面レイアウトのデザイン案は顧客から支給され、当社側では微修正のみを想定する。」
スコープ・機能規模の根拠
項目例
- 画面数・帳票数の想定
- IF本数と難易度
- データ件数・データ量
例文
- 「画面数はヒアリング結果と現行システムのメニュー構成から、業務画面15、マスタ画面5、管理画面3の計23画面と想定している。」
- 「外部IFは、顧客提供のRFPに記載のある『会計システム連携』『人事システム連携』の2本を対象とし、各1日1回のバッチ連携を想定する。」
工数見積りの根拠
項目例
- 使用した見積り手法
- 係数・工数単価
- バッファの考え方
例文
- 「要件定義工数は、ヒアリング対象部署3部門(各2回)+要件定義書作成・レビューを合計して、1部門あたり24時間×3部門=72時間と算出した。」
- 「技術的な不確実性(新ミドルウェア導入)を考慮し、設計・実装工程に対して10%のバッファを上乗せしている。」
コスト・期間の根拠
項目例
- 作業人数と期間の関係
- スキルレベル別のアサイン想定
- カレンダー・稼働日数
例文
- 「実装〜単体テストは、SE1名+PG2名の体制で2ヶ月間(営業日合計40日、1人あたり8時間)を想定している。」
- 「レビューや打ち合わせは週1回1時間を基本とし、1回あたりPM+SEの2名参加とした。」
リスクと不確実性の扱い
項目例
- リスク一覧
- 影響度と対応方針
- リスクバッファ
例文
- 「要件の確定度合いが低いため、追加・変更発生リスクが高いと判断し、全体工数の10%をリスクバッファとして見込んでいる。」
- 「外部システムとのIF仕様が未確定であることから、IF1本あたり8時間分の調整工数を追加で計上している。」
対象外・別途見積り項目
項目例
- 対象外の機能
- 対象外の業務
- 別途見積りとする項目
例文
- 「現行システムからのデータ移行は、別途見積りとし、本見積りには含まない。」
- 「操作マニュアルの作成は、標準的な画面操作説明のみを対象とし、業務フローの再設計は対象外とする。」
よくあるNGパターンと改善例
経験と勘だけの説明
- 「過去もこれくらいだったので同じくらいです」
- 「この規模なら2ヶ月くらいでしょう」
改善例:
- 「直近の類似案件(顧客A社向け販売管理システム)では、同規模の機能で実装〜単体テストまで合計300時間であったため、本案件も同程度と見込み、画面数の差分(+20%)を加味し360時間とした。」
前提条件が書かれていない
後から「そんなつもりではなかった」と揉める原因になります。
改善例:
- 「本見積りでは、『現行システムに大きな仕様変更はない』ことを前提としています。現行仕様の見直しや業務プロセス改革が必要な場合は、別途見積りとなります。」
バッファを隠す
バッファを隠していると、「削れませんか?」と言われたときに守り切れません。
改善例:
- 「技術的な不確実性および要件変更リスクに備え、合計工数の10%(80時間)をリスクバッファとして計上しています。バッファの具体的な使用状況は、定例会で共有します。」
見積り根拠をレビュー・更新するポイント
チームレビューで穴を埋める
- 開発メンバーに「この工数で本当に足りるか」をレビューしてもらう
- テスト担当、インフラ担当など、専門視点からもチェックしてもらう
レビューで得られた指摘は、数字だけでなく根拠の文章にも反映することで、見積りの説得力が増します。
見積り根拠は「生きたドキュメント」にする
- 要件変更や追加があれば、その都度根拠も更新する
- プロジェクト完了時に、「実績」と「見積り根拠」を突き合わせ、次回の改善に活かす
こうすることで、見積り根拠が次のプロジェクトの「武器」になっていきます。
まとめ
最後に、この記事の要点を整理します。
- 見積り根拠は、数字の裏側を説明するための前提・計算方法・参照実績のセット。
- 「前提条件」「スコープ」「工数の算出方法」「バッファの考え方」「対象外」を明文化することで、説明責任と将来の自分を守れる。
- 類推見積り・ボトムアップ・パラメトリックなど、手法ごとに「何を根拠にしたか」を書き分ける。
- カタログ形式で文例をストックしておくと、案件ごとに少しアレンジするだけで、短時間で説得力のある見積り根拠が作れる。
- 見積り根拠は作って終わりではなく、レビューと更新を通じて磨き込むことで、組織としての見積り力が向上する。