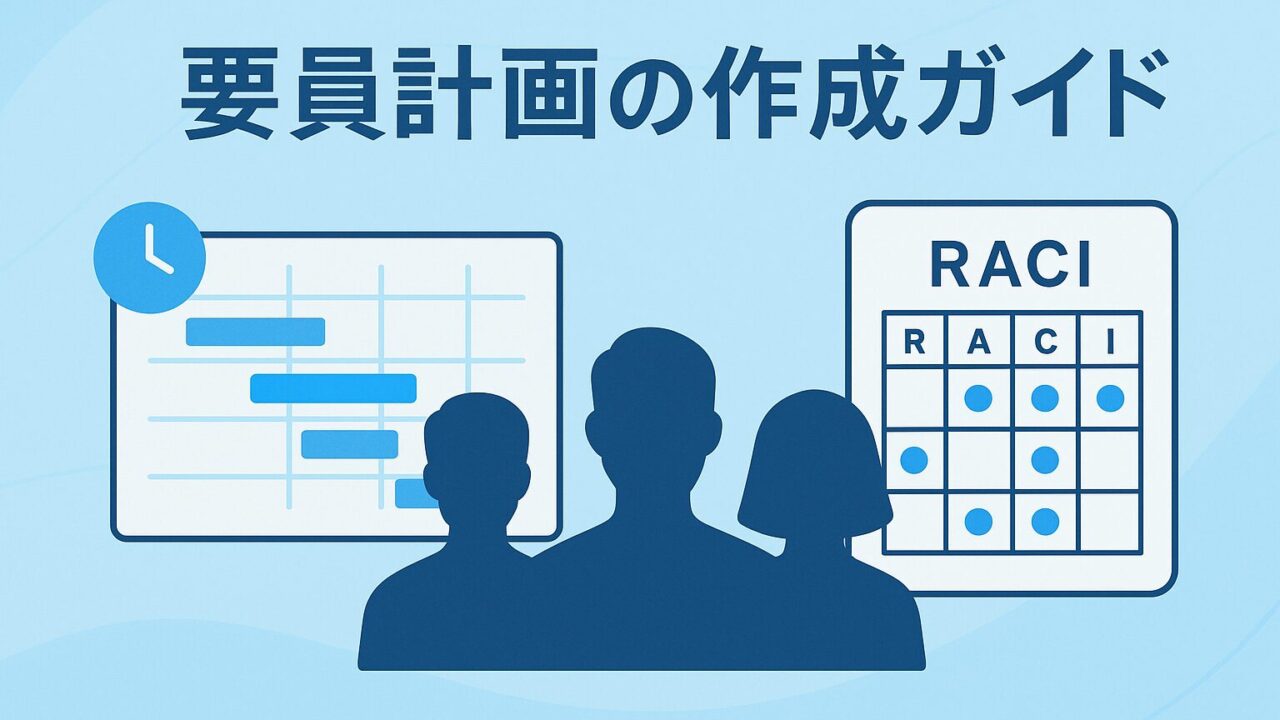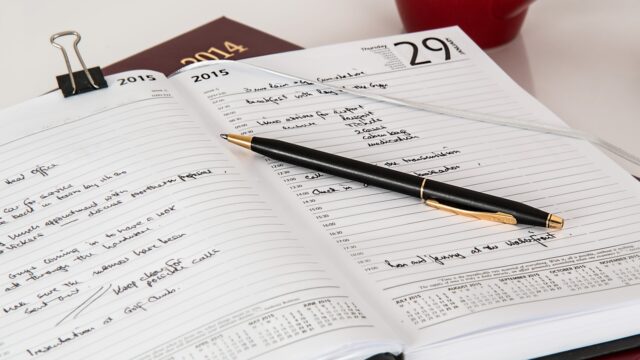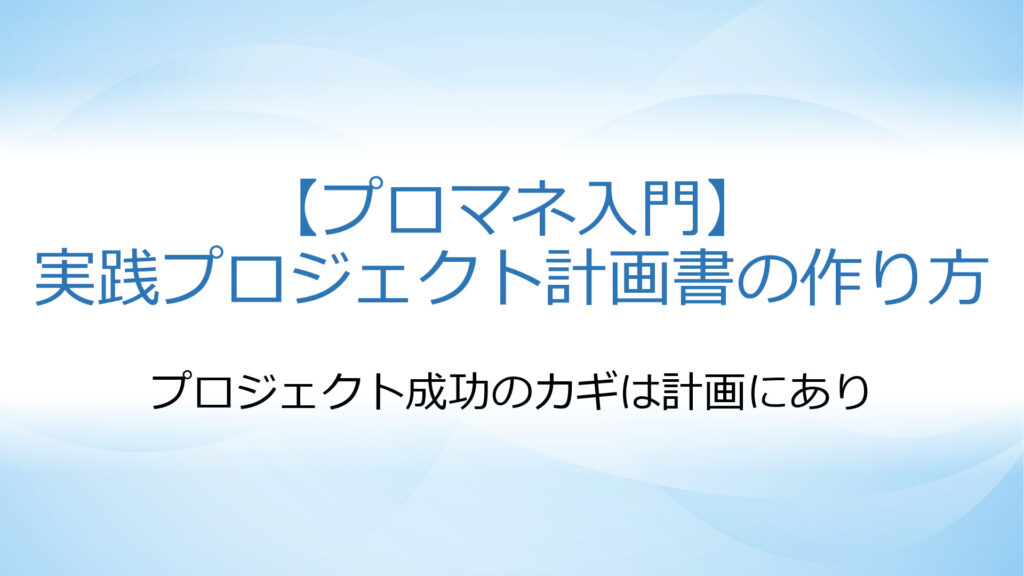【目次】
・要員計画の説明
- 要員計画とは
- スケジュールと要員計画の関係性
・要員計画の作成
- 作成手順
- つまずきやすいポイントと対策
・まとめ
要員計画の説明
要員計画は、プロジェクトに「いつ・誰が・どのスキルで・どれだけ」参画するかを設計し、スケジュールとコストの実現性を高める基盤です。
本稿では、スケジュールとの関係、作成手順、運用ポイントについて解説します。
要員計画作成で活用できる資料はこちらからダウンロードできるので、そちらもご活用ください。
要員計画とは
要員計画(Resource/Staffing Plan)は、「いつ・誰が・どのスキルで・どれだけの時間」プロジェクトに参加するのかを、コストやスケジュールと整合させて定義する計画です。
この要員計画を作成する目的は次の3つです。
- 実行可能性の確保:必要な人・スキル・工数が揃っていることを事前に確認
- 調達・調整の早期化:採用、外部委託、兼務調整、教育を計画的に実施
- 可視化と合意:関係者(上位管理者、ライン長、ベンダー)と“人の割き方”を明文化して合意
要員計画には、以下の要素が含まれます。
- 役割と責任(例:RACI、責任分担表)
- スキル要件(必須/尚可、レベル定義)
- 人数・工数・稼働率(期間別のFTE配分)
- 参画タイミング(オンボーディング/離脱の時期)
- 入手方法(社内アサイン、外部調達、教育)
- コスト(人件費、委託費、教育費)
- ガバナンス(承認フロー、変更管理、欠員時の代替)
スケジュールと要員計画の関係性
要員計画はスケジュールと相互依存です。ポイントは以下の通りです。
クリティカルパスと技能の一致
クリティカルな工程に必要なスキルを必要なタイミングで確保できないと即遅延につながります。
例えば、要員定義でドメイン知識者を確保できなければ、以降の設計・開発作業が全て遅延します。
負荷平準化(リソースレベリング)
同一メンバーに過度な割当が集中すると、品質低下・遅延・離職リスクが増加します。
それを回避するため、作業量と作業状況を比較しながらスケジュールを調整します。
例えば「1か月だけ負荷が高いタイミングがある」という場合、1か月だけ要員を調達するのではなく、前後の月に作業を分散させて平準化することが多いです。
計数の整合(FTE/工数 vs 期間)
プロジェクト作業以外にも、休暇や社内行事、研修などの時間を考慮する必要があります。
そのため、メンバの可用工数と割当工数の整合を確認します。
- 可用工数=(所定労働時間 − 休暇・会議・兼務)× 期間日数
- 負荷率(%)= 割当工数 ÷ 可用工数 × 100
- FTE目安:0.8前後までが持続的、1.0超が常態化する計画はリスキー
変更管理
要件変更や障害多発などで工数が増えると、要員計画、スケジュール、コストを同時に調整する必要があります。
要員計画の作成
作成手順
要員計画は下記の8ステップで作ると、抜け漏れが少なくなります。
ステップ1:前提の整理(期間・予算・制約)
- プロジェクト期間、主要マイルストーン、総予算、上限人件費、兼務比率、勤務体系(裁量/固定、残業制限)、法定休日・長期休暇など
- 既定の制約(例:特定フェーズは社内メンバー必須、セキュリティ要件で外注制限 など)を明記
ステップ2:役割と責任(RACI)を定義
- 主要成果物や意思決定ごとにR(責任者)/A(最終責任)/C(協議)/I(通知)を割当
- 例:
- 要件定義書:R=ビジネスアナリスト、A=PM、C=顧客PO、I=品質管理担当
- リリース可否:R=リリースマネージャ、A=PM、C=開発/運用責任者、I=顧客窓口
ステップ3:スキル要件とレベル定義
- 役割ごとに必須スキル(例:Java 8以上、AWS基礎、要件ヒアリング)とレベル(入門/基礎/実務/上級/エキスパート)を定義
- 代替スキルや育成前提(オンザジョブ/短期研修)も記載して供給可能性を高める
ステップ4:工数見積りとFTE配分
- WBS/見積りから工程別・役割別の工数を算出
- FTE(人月)算出の基本式
- FTE = 必要工数(時間) ÷(1人の月可用工数)
- 負荷率チェック:メンバー単位で割当工数 ÷ 可用工数を算出し、80〜90%を上限目安に設定
- 例(簡略)
- 期間:4か月、1人可用=120h/月(会議や兼務控除後)
- 必要工数:設計600h、実装1200h、試験900h
- 設計FTE=600/120=5人月、実装=10人月、試験=7.5人月 → 月別FTEに展開。
ステップ5:参画計画(オンボーディング〜離脱)
- 参画時期:いつ入るか/Ramp-up期間(環境構築、ドメイン学習)を確保
- 離脱時期:引継ぎ・文書化・運用教育の工数を計上
- キーパーソンの重畳:フェーズ切替時に、既存リーダーが後続リーダーを一定期間重ねて配置し、知識移転を確実にする
ステップ6:入手方法(調達・育成・代替案)
- 社内アサイン:ライン長と事前調整(兼務率・評価配分)
- 外部委託:期間、成果物定義、NDA/セキュリティ条件、受入れ条件(成果物レビュー基準)を明確化
- 育成:短期研修(2〜5日)やメンター制度、ペア作業を計画に組み込む
- 代替案:急な欠員時のバックアップ要員リストと呼び出し手順
ステップ7:コストと承認
- 役割別単価×FTEで人件費見積りを作成(外部は見積書、社内は標準原価)
- 予算に収まらない場合は、優先度の低い作業の削減、スケジュール再設計、スキル構成の見直し(上級1→中級2など)で最適化
- 承認フロー(PM→部長→ステアリングコミッティなど)を明文化
ステップ8:可視化・モニタリング・変更管理
- 可視化:週次で役割別FTEの実績vs計画、メンバー別負荷率、欠員・新規参画の予定表を共有
- 指標:
- 充足率=(確保FTE ÷ 必要FTE)×100
- 欠員日数=要員未充足の日数合計
- オンボーディング遅延数=予定よりも参画が遅れた人数
- 変更管理:要件変更・障害増・品質課題で工数が増えた場合、要員計画・スケジュール・コストを同時改訂し再承認。
つまずきやすいポイントと対策
- 兼務前提の過小見積り
- 対策:会議・雑務・社内行事の平均時間を差し引いた可用工数の標準値を使う
- スキル偏在(特定の上級者に集中)
- 対策:ペア作業やレビュー権限の分散、属人タスクの分解
- オンボーディング不足
- 対策:初月に環境構築/ドメイン学習/手順訓練の工数を明記
- 外部委託の受入れ基準が曖昧
- 対策:ドキュメント品質基準、テスト通過条件、レビュー観点の合意文書化
- 要件変更時に人だけ増やす
- 対策:スケジュール再計画とセットで判断
ブルックスの法則に注意(人を増やすほど遅れることがある)
- 対策:スケジュール再計画とセットで判断
まとめ
要員計画は、役割・スキル・FTE・参画タイミング・入手方法・コストを、スケジュールと整合させて合意するための中核計画です。
作成は8ステップ(前提→RACI→スキル→工数/FTE→参画→入手→コスト→モニタリング)で進めると実務に乗りやすいです。
つまずきやすい点(兼務、属人化、受入れ基準、オンボーディング不足)を事前に設計し、リソースレベリングで持続可能な負荷を維持することが、品質と納期を両立させる近道です。